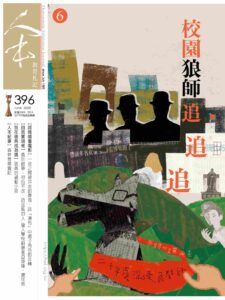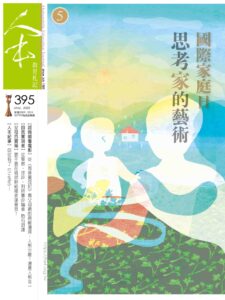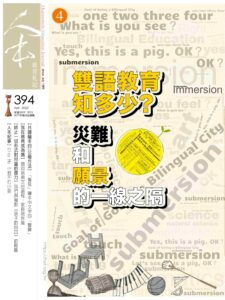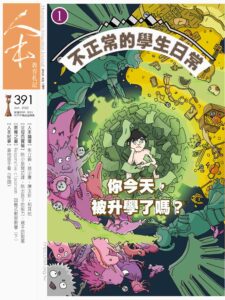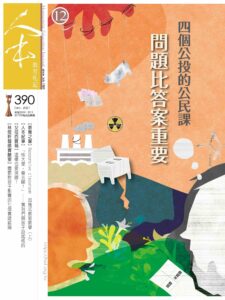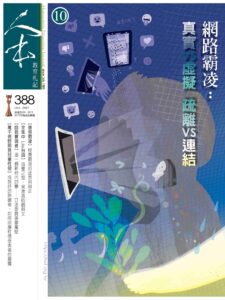日本守護兒童、保障兒童權利的結構

前言
在日本,作為防止兒童遭受體罰或虐待、保障兒童權利的代表性組織有「兒童相談所」與「兒童監察員(ombudsperson)」。
兒童相談所是基於兒童福祉法設立的組織,基本上,是因應日本的行政單位都道府縣中的人口數而設立的多個單位(特別的市鎮與東京都的各區也都有設置)。相對於此,兒童監察員則不是基於法律所設立,而是依據都道府縣或是市區町村的條例所設置的。
以下,我將分別為各位介紹這兩個單位各自的結構。日本曾受聯合國兒童權利委員會勸告,要求要設立孩童監察員等獨立監視機構(independent monitoring),然而日本於2022年6月15日所立法的兒童基本法中,忽略該勸告,至今並未實現。
兒童相談所
兒童相談所是基於兒童福祉法,基本上設置於行政單位都道府縣中,兒童相談所的權限有
一、接受來自與兒童有關的家庭養育等相關諮商
二、兒童與家庭相關的調查與判定
三、針對兒童及照護者提供必要的指導
四、對來自需要保護家庭的兒童提供暫時保護與之後的親子隔離安置的執行(寄養家庭、兒童養護設施等的安置)
五、其他權限。


其特徵是,對於家庭具有支援與強制力等保護兒童的兩個極端面。
兒童相談所在防止兒童虐待上,扮演著主要角色。在日本的兒童虐待防止法中,發現兒童疑似遭受虐待的人,必須負起通報之責,向相關單位通報,首先以基本行政單位市區町村為主(有時也會向兒童相談所通報)。而接收到民眾通報的市區町村則必須在48小時內確認兒童安全狀況。
如果確認結果是,判斷為必須進一步確認兒童安全或是有必要進行安全確保程序時,市區町村就必須將案件傳達給兒童相談所,而兒童相談所就能要求市區町村出面進行調查或是由兒童相談所介入調查。依情況不同,必要時也能在取得法院的令狀後,進行臨檢與搜索。萬一,市區町村經判斷,認為有必要提供兒童緊急的保護等措施時,則由兒童相談所提供兒童暫時保護措施。然而,有時這種暫時保護措施,會變成長期性措施。基於對此作法的批判,在2022年6月8日成立的兒童福祉法改正條文中,明令暫時保護措施需要有法院的令狀(暫時保護令)始能為之(兒童相談所必須在事前或是保護開始七天內,以書面提出申請)。
經過上述程序後,當市區町村判斷案件為,照護者虐待兒童,意即原本受照護者監護的兒童其福祉遭受侵害時,兒童相談所必須要取得法院的認可後,始得將兒童委託給寄養家庭或是安排兒童進入育幼院、兒童養護設施等機構。
當受害兒童完成安置後,兒童相談所將對兒童照護者進行支援與指導,一般為期兩年,以謀求兒童家庭的完整(有時會延長)。
兒童監察員
相對於兒童相談所,兒童監察員並非基於兒童福祉法與兒童虐待防止法所設立,而是基於日本的都道府縣與市區町村等自治體的條例所設置的(條例上的名稱有的是用兒童監察員,有的是用兒童的權利擁護委員,有的則是用兒童的權利救濟委員等名稱。另外,也有不少例子是使用兒童感覺親切的暱稱)。兒童監察員相關條例之外,也另設置了兒童的權利條例。而且,在並未制訂類似條例的自治體中,則不會有兒童監察員。因此,截至2022年4月的現在,全日本共有43個自治體並未設置兒童監察員。日本的自治體數有都道府縣47個、市區町村有1741個,從整體來看並不算多,而且目前設置兒童監察員的自治體有增加的趨勢。
兒童監察員多由法律、心理、教育、福祉等多業種的專家擔任,一般是設置所謂的相談室等的相談窗口後就開始營運。雖然在條例上,明文註明了針對兒童權利遭受侵害的救濟與諮商內容,但只要當兒童感到困擾、受苦與難受時,即可就近接受諮商。兒童監察員與兒童相談所不同,兒童監察員的特徵在於,本身並不是特定的專業領域,能更廣泛地救濟更多兒童。另外,由於曾發生兒童的權利侵害事例,因此兒童監察員也具有針對自治體提出制度改善的提議與勸告的權限,並進一步扮演推動兒童權利普及與推廣的角色。
兒童監察員也會觸及到包含學校體罰等不適當對待與家庭內虐待等問題,萬一遭遇類似狀況,兒童監察員有權充分聆聽兒童的意見,進一步與校方協調,也能與兒童相談所合作一起解決問題。
總結
以上,我聚焦在兒童相談所與兒童監察員,概括地為各位說明關於兒童的權利遭受侵害,尤其是包含不適切對待兒童等的虐待行為,將兒童從體罰救出的救濟狀況。這兩個機構其由來與法律上的根據雖皆有異,卻都具有其存在的意義。另外,雖然是相異的兩組織,但在將兒童從體罰中救出這一點上經常會處理共通的案例。具有法律權限應對兒童的家內體罰(虐待)的是兒童相談所,但如果就容易諮商這一點來看,則是兒童監察員略勝一籌;兒童監察員除了與兒童相談所合作解決問題之外,有時也會採用與兒童相談所不同的觀點來解決問題。
原文
日本における子どもを守り、権利を保障するしくみ
野村武司(東京経済大学教授・子どもの権利条約総合研究所副代表)
- はじめに
日本において、子どもを体罰または虐から守り、子どもの権利を保障するしくみの代表的なものとして、児童相談所と「子どもオンブズパーソン」がある。
児童相談所は、児童福祉法に基づくしくみで、基本的には、全ての都道府県に、人口等に応じて複数設置されている(特別の市及び東京都の区等も設置できるとされている。)。これに対して、子どもオンブズパーソンは、法律に基づくしくみではなく、都道府県や市区町村の条例で設置されているものである。
以下、それぞれについて、そのしくみについて紹介することとする。なお、日本は、国連・子どもの権利委員会から、子どもオンブズパーソンなど、独立した監視機関(independent monitoring)を国に設置することについて勧告を受けているが、2022年6月15日に成立した子ども基本法では、その設置が見送られ、実現していない。
- 児童相談所
児童相談所は、児童福祉法に基づいて、基本的に都道府県に設置され、①子どもに関する家庭等からの養育等の相談、②子ども及び家庭についての調査、判定、③子ども及び保護者に対する必要な指導、④保護が必要な家庭からの子どもの一時保護とその後の親子分離の措置(里親委託、児童養護施設等への入所措置)、⑤その他の権限を持っている。家庭に対する支援と強制力を伴った子どもの保護の両側面を持っているのが特徴である。
児童相談所は、児童虐待の防止等について、中心的役割を担っている。児童虐待防止法では、児童虐待を受けたと思われる子どもを発見した者は、「通告しなければならない」とされ、その通告先は、まずは、基本的に市区町村で(児童相談所に通告がなされる場合もある。)、通告を受けた市区町村等は、48時間以内に子どもの安全を確認するという運用がなされている。
その結果、さらに安全の確認や安全確保の手続をとる必要があると判断される場合には、ケースは、市区町村から児童相談所に送致され、児童相談所は、調査のための出頭要求、立入調査、場合によっては、裁判所の令状を得た上での臨検・捜索等を行うことができる。そして、緊急的に保護等が必要であると判断される場合には、児童相談所は子どもの一時保護を行う。なお、一時保護は、もっぱら行政上の措置として長期にわたることもあり、これに対する批判から、2022年6月8日に成立した児童福祉法改正で、一時保護には、裁判所の令状(一時保護状)が必要となった(児童相談所は、事前または保護開始から7日以内に書面で請求しなければならない。)。
こうした手続等の後、保護者が子どもを虐待するなど、保護者に子どもを監護させることが子どもの福祉を害すると判断される場合には、児童相談所は、裁判所の承認を得るなどして、子どもを里親に委託したり、乳児院、児童養護施設に入所させる等の措置をとることとなる。
こうした措置がとられた場合、児童相談所は、保護者の支援・指導を行い、2年を目途に、子どもの家庭への統合を図る(延長もある。)。
- 子どもオンブズパーソン
これに対して、子どもオンブズパーソンは、児童福祉法や児童虐待防止法といった法律に基づくものではなく、都道府県や市区町村といった自治体の条例に基づいて設置されているものである(条例上の名称は、オンブズパーソンを使用するものもあれば、子どもの権利擁護委員、子どもの権利救済委員などの名称もある。子どもが親しみを持てる愛称がつけられている例も多い。)。子どもオンブズパーソンに関する条例の他、子どもの権利条例で設置されている。したがって、こうした条例を制定していない自治体では、子どもオンブズパーソンは設置されていない。2022年4月現在、43の自治体で設置がなされている。日本の自治体数は、都道府県が47、市区町村が1741であるので、全体として必ずしも多いとは言えないが、設置する自治体が増えている。
子どもオンブズパーソンは、法律、心理、教育、福祉といった多職種の専門家が担うことが多く、相談室などの相談窓口を作って運営されるのが通例である。子どもの権利侵害からの相談と救済というのが条例上の位置づけであるが、子どもが困っていたり、苦しんでいたり、つらかったりした場合に相談できるという運用がなされている。児童相談所とは異なり、特定の専門分野ではなく、広く子どもの救済に当たる点に特徴がある。また、子どもの権利侵害事例等をきっかけとして、自治体に対して制度改善を提案・勧告する権限、さらに子どもの権利を普及・啓発する役割を有している。
子どもオンブズパーソンには、学校での体罰を含む不適切な対応、家庭での虐待等の問題等も寄せられており、そうした場合、子どもオンブズパーソンは、子どもの意見を十分に聞き、これを踏まえた上で、学校と調整をしたり、児童相談所等とも連携をして問題の解決に当たることになる。
- まとめ
以上、児童相談所と子どもオンブズパーソンに焦点を当てて、子どもの権利侵害、とりわけ子どもの不適切な取扱いを含む虐待、体罰からの子どもの救済について概観した。両者は、その由来や法律上の根拠も異なるものであり、それぞれに存在意義がある。また、異なる機関でありながら、子どもの体罰からの救済という点で共通のケースを扱うことも多い。子どもの家庭での体罰(虐待)を、法律上の権限をもって対処するのは児童相談所であるが、相談のしやすさという点では、子どもオンブズパーソンが勝っており、児童相談所と連携しながら解決がなされる他、児童相談所とは別の視点から調整をする中で問題を解決することもある。
如何給孩子更好的教育?為人父母/教師的您,是否正在追尋答案?進步的源頭,來自不斷的思索與釐清。《人本教育札記》多次榮獲金鼎獎、金蝶獎的肯定!國內第一本為家長及關心教育者所編寫的專業教育月刊,提供您看教育的不同角度。每個月都陪您,一步一步向前,充實自己。
- 本期特企